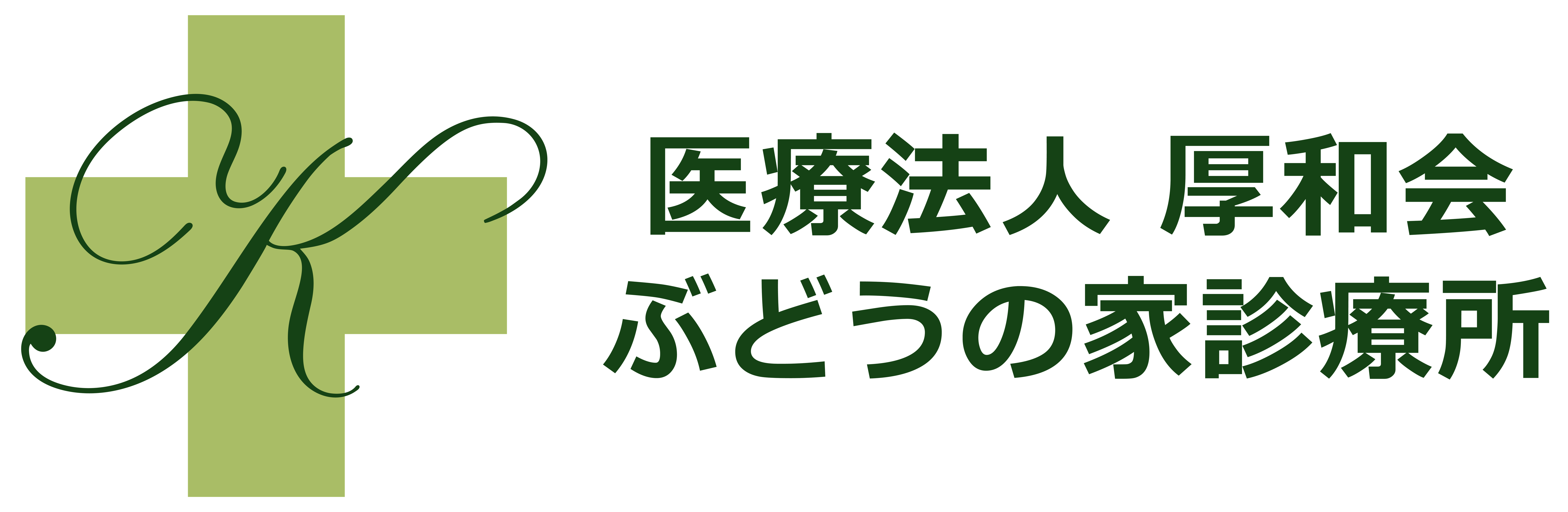【羽曳野市近く】内科とはどこまで何を見てくれる?外科や他診療科の違い
Internal Medicine

厚和会「ぶどうの家診療所」の内科は羽曳野市(富田林市/柏原市エリア※駒ヶ谷駅・古市駅周辺)で幅広い症状を見る窓口として機能します。
「子供が熱を出したけれど、内科と小児科どちらに行ったらいい?」
「親が胸の違和感を訴えているけれど、循環器内科なのか普通の内科でいいのか迷う。」
体調不良の際に、「何科を受診すればよいのか」迷うことがあるのではないでしょうか。特にお子さんや高齢のご家族の場合は、判断が難しいと思います。
ここでは、内科で診察する病気や他の診療科との違い、いろいろな内科のそれぞれの役割について解説します。
受診する診療科に迷ったときの助けになれば幸いです。
お気軽にお問い合せ下さい
TEL.072-950-0155
受付時間 9:00~17:30
※水曜日、日曜日、祝日、土曜日(午後)は除く
もしくは下記フォームよりお問い合わせください。
問い合わせフォーム
内科とは
内科は、あらゆる体の不調に対する「最初の相談窓口」となる診療科です。
内臓、神経、血液など体の内側で起こる病気を診断し、手術ではなく薬物療法や生活指導を中心とした治療を行います。
患者さん一人ひとりの生活全般に目を向け、病気の回復や健康維持を支える役割があります。
(参考:職業情報提供サイト 内科医|厚生労働省)
内科の基本的な役割
内科の役割は、問診や診察により体調不良の「原因を調べ、病気を特定すること」です。
必要に応じて、尿検査、血液検査、超音波検査、心電図検査などの各種検査も行います。
これらのデータを分析し、総合的に判断して病名を診断します。
このため、内科はあらゆる体調不良に対して、最初の相談窓口として機能するのです。
どの診療科を受診すべきか判断がつかない場合、最初に内科を受診することで適切な医療を受けられます。
また、内科には他の診療科へつなぐ役割があり、より専門的な治療が必要と判断した場合は、症状に合った専門医を紹介いたします。
内科の診療範囲はどこまで
内科で診察する病気の範囲は、臓器の限定はしていません。
薬物治療や生活習慣の改善といった、基本的に手術を必要としない治療を行います。
風邪やインフルエンザのような急性の病気から、高血圧や糖尿病といった長い期間で治療が必要な病気まで、薬で治療できる病気のほとんどが内科の範囲です。
日常的な症状の診察から、特定の臓器を専門とする治療や入院が必要な重症患者さんの治療など、非常に幅広い領域を担当します。
クリニックや診療所などは、外来を中心とした地域に密着した医療活動が主な仕事です。
一方、大学病院や総合病院などの大きな病院では、先端医療に関わりながら、他の診療科の医師と連携して専門的な治療を行います。
同じ「内科」でも、診療の場によって役割や特徴が変わります。
(参考:一般社団法人 日本内科学会)
内科で診察できる疾患
内科で扱う疾患について、具体的に説明します。
発熱や咳など身近な症状から、継続した管理が必要な生活習慣病まで、幅広く対応しています。
よくある症状(発熱・咳・腹痛など)
日常生活で感じるちょっとした体調不良のほとんどは、内科に相談できます。
たとえば以下のような症状があらわれた場合は、内科を受診してください。
| 部位 | 症状 |
|---|---|
| 全身 | 発熱、悪寒、体のだるさ、疲れやすい、食欲不振、むくみ |
| 呼吸器 | 咳、痰、のどの痛み、鼻水、鼻づまり、息苦しさ |
| 消化器 | 腹痛、胃もたれ、吐き気・嘔吐、下痢、便秘 |
| その他 | 頭痛、めまい、立ちくらみ、動悸、関節の痛み、しびれ |
これらの症状は、軽い風邪から重い病気のサインまで含まれるため、内科での早期診断が重要です。
内科で診ることが多い感染症(風邪・インフルエンザ・新型コロナなど)
内科に来院される原因のひとつが、ウイルスや細菌による感染症です。
| 疾患 | 病状・主なリスク |
|---|---|
| かぜ症候群 | 鼻水、くしゃみ、のどの痛み、咳、発熱といった症状が特徴で、適切な薬の処方や対症療法によって症状の緩和をはかります。 |
| インフルエンザ | 38℃以上の高熱、強い関節痛や筋肉痛、頭痛、倦怠感といった全身症状が急激に現れるのが特徴です。 迅速診断キットによる検査で診断し、抗ウイルス薬による治療を行います。 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 発熱や空咳、呼吸困難、倦怠感のほか、味覚・嗅覚障害などが特徴的な症状として知られていますが、変異株によって症状が異なります。 感染が疑われる場合は、指定された手順に従って受診してください。 |
| その他の感染症 | のどの強い痛みを伴う「扁桃炎」、吐き気や下痢を引き起こす「感染性胃腸炎」、排尿時の痛みや頻尿がみられる「膀胱炎」、肺の炎症である「肺炎」なども、内科で診断・治療します。 |
内科で対応できる生活習慣病(糖尿病・高血圧・脂質異常症など)
急な症状だけでなく、長期的な健康管理も重要な役割です。
食生活や運動習慣、喫煙、飲酒といった生活習慣がかかわる「生活習慣病」の管理は、内科の専門分野です。
代表的な生活習慣病として、次のようなものがあります。
| 生活習慣病 | 病状・主なリスク |
|---|---|
| 高血圧 | 血圧が高い状態が続く病気で、自覚症状がないまま進行し、心臓病や脳卒中のリスクを高めます。 動脈硬化や心筋梗塞、脳卒中といった命に関わる病気を引き起こす原因になります 。 |
| 糖尿病 | 血糖値が高くなる病気で、進行すると全身の血管や神経にダメージを与え、様々な合併症を引き起こします。 「網膜症(失明の原因)」「腎症(透析が必要になることも)」「神経障害(足の壊疽)」という三大合併症のリスクになります。 |
| 脂質異常症(高コレステロール血症) | 血液中の脂質(コレステロールや中性脂肪)が異常な値を示す状態で、動脈硬化の主な原因となります。 |
| 心臓病 | 高血圧や脂質異常症などが動脈硬化を進行させ、心臓に血液を送る血管が狭くなると狭心症、詰まってしまうと心筋梗塞を引き起こします。 日本人の死因の上位を占める重大な疾患です。 |
| 脳血管障害(脳卒中) | 高血圧に伴い、脳の血管が詰まったり(脳梗塞)、破れたり(脳出血)する脳卒中を起こしやすくなります。 命に関わるだけでなく、重い後遺症が残る恐れもあります。 |
| 高尿酸血症 | 血液中の尿酸値が高い状態です。 ある日突然、足の親指の付け根などに激しい痛みを引き起こす「痛風発作」の原因となります。 |
| 肥満症 | 体重が多い状態を肥満といい、多くの生活習慣病のリスクとなります。 治療が必要な病気などを合併した状態が肥満症です。 |
(参考:生活習慣病などの情報|厚生労働省)
これらの病気は、長期的な治療が必要となる場合が殆どです。
内科医は定期的な診察や検査を通じて患者さんの状態を把握し、薬による治療と食事や運動に関するアドバイスを行います。
内科と他の診療科との違い
内科の役割がわかると、「外科」と「小児科」といった他の診療科との違いが気になるかもしれません。
それぞれの科の役割を説明します。
内科と外科の違い
内科と外科の簡単な区別方法は、大まかにいうと手術を行うかどうかです。
内科:主に薬による治療や生活習慣の改善指導により、病気を治療します。基本的に手術は行いません。
外科:主に手術により、病気やケガを治療します。
胃潰瘍を例にあげると
- 薬で炎症を抑えて治す場合は「消化器内科」
- 潰瘍部の出血が止まらない・穴が開いているといった、手術が必要な状態では「外科」
怪我や、明らかに手術が必要そうな症状の場合は外科、原因不明の体調不良や慢性的な病気の管理は内科と理解しておくと良いでしょう。
内科と小児科との違い
小児科の対象年齢に具体的な規定は設けられていませんが、新生児から中学生までが一般的です。
内科は主に成人(一般的に15歳、高校生以上)を対象とし、小児科は新生児から乳幼児、学童、思春期(中学3年生頃まで)の子どもを専門に診療すると考えると良いでしょう。
内科と小児科で区別するのは、子供は大人とは体の仕組みや病気の反応が大きく異なり、また、子供特有の病気も数多くあるためです。
ただし幼少期から慢性的な疾患で治療を受けているなど特別な場合、引き続きかかりつけの小児科医に見てもらう方が良いケースもあります。
小児科から内科への移行のタイミングについては、かかりつけの小児科医に相談してください。
適切なタイミングで内科への紹介状を書いてくれるでしょう。
内科系診療科の種類
「内科」と一言で言っても病院によっては「循環器内科」「消化器内科」など、さまざまな内科にわかれていることがあります。
それぞれの役割について、簡単に紹介します。
なお、これらは一例であり、医療機関によっては内容が異なる場合もあります。
総合内科の役割
まずは、「内科」または「一般内科」と「総合内科」について説明します。
街で見かける何もつかない「内科」は「一般内科」とも呼ばれ、幅広い内科系疾患に対応します。
一方で、大学病院などの大きな病院では「総合内科」を設けているところも。ここでは症状がはっきりせず、どの診療科を受診したらよいかわからない患者さんや、いくつかの病気を抱えている患者さんを最初に診察し、適切な専門科に振り分ける役目を担うのです。
循環器内科・呼吸器内科・消化器内科
特定の臓器を専門とする内科です。
| 診療科 | 特徴 |
|---|---|
| 循環器内科 | 「循環器」とは血液を全身に送り出すシステムのことで、循環器内科は心臓や血管の病気を専門とします。 動悸、息切れ、胸の痛みといった症状や、高血圧、不整脈、狭心症、心不全などの診断・治療を行います。 |
| 呼吸器内科 | 肺や気管支など、呼吸に関わる臓器の病気を専門とします。 長引く咳、痰、呼吸困難などの症状がある場合や、気管支喘息、肺炎、COPD(慢性閉塞性肺疾患)などの診断・治療を行います。 |
| 消化器内科 | 食道、胃、十二指腸、大腸といった消化管と、肝臓、胆のう、膵臓といった臓器の病気が専門です。 腹痛、胸やけ、下痢、便秘、血便などの症状や、胃炎、胃潰瘍、逆流性食道炎、肝炎、大腸ポリープなどの診断・治療を行います。 |
糖尿病・代謝内科、腎臓・内分泌内科
これらは主に体の代謝や、ホルモンに関する病気を専門とします。
| 診療科 | 特徴 |
|---|---|
| 糖尿病・代謝内科 | 血糖値が慢性的に高くなる糖尿病や脂質異常症、肥満症などの非感染性疾患に関する病気を専門とする内科です。 健康診断で血糖値やコレステロール値の異常を指摘された場合などが対象です。 |
| 腎臓・内分泌内科 | 急性・慢性腎臓病やネフローゼ症候群など腎疾患や、甲状腺や副腎などホルモンを分泌する内分泌器官の病気が専門です。 |
血液・腫瘍内科、アレルギー・リウマチ内科
血液や免疫にかかわる病気が専門です。
| 診療科 | 特徴 |
|---|---|
| 血液・腫瘍内科 | 血液の成分(赤血球、白血球、血小板)の異常によって起こる貧血、白血病などの病気や、がん(悪性腫瘍)を含む血液疾患の診療を行います。 |
| アレルギー・リウマチ内科 | 花粉症などのアレルギー疾患や、関節リウマチなどの膠原病といった、免疫システムの異常によっておこる病気の診断・治療を行います。 |
脳神経内科、心療内科
神経や心と体のバランスに関する疾患を専門とする内科です。
| 診療科 | 特徴 |
|---|---|
| 脳神経内科 | 脳・脊髄・末梢神経・筋肉の病気を診療します。 頭痛やめまい、パーキンソン病、アルツハイマー病などが対象疾患です。 |
| 心療内科 | ストレスを感じると起こる頭痛や胃腸症状などの心身症を専門とし、身体・心理・行動面から診療を行います。 |
何科に行くか迷ったら
内科の役割や種類について説明してきましたが、実際に家族が体調を崩した時などは冷静な判断は難しいでしょう。
いざという時の対応方法を紹介します。
かかりつけ医に相談
何科に行くか迷った時は、まずは「かかりつけ医に相談」しましょう。
施設によっては電話で相談に乗ってくれるところもあるので、迷った場合の心強い味方です。
かかりつけ医を持つことは、日常的に単に便利なだけでなく、いざという時に相談できるので頼りになります。
救急相談窓口・健診・オンライン診療の活用方法
かかりつけ医がいない場合や、夜間・休日など急な体調不良で困った場合は、公的な相談窓口や施設のサービスを利用する方法があります。
ただし、初診時や症状によっては対面での診療が必要な場合もあるため、医療機関にご相談ください。
(参考:総務省消防庁、厚生労働省、上手な医療のかかり方)
内科に関するよくある質問
- 内科では何を診てもらえますか?
-
内科は、体の内側にある臓器の病気を診断・治療する診療科です。
風邪やインフルエンザといった急性疾患から、高血圧や糖尿病といった生活習慣病まで、幅広い病気を扱います。
専門的な治療が必要な場合は、最適な専門医を紹介する「総合的な窓口」としての役割も担います。
- 内科で皮膚の症状は診てもらえますか?
-
症状によりますが、相談は可能です。
比較的軽度な疾患であれば、内科で初期対応をすることがあります。
また、内科的な病気が原因で皮膚に症状が現れることもあるため、内科医が全身の状態から判断することも重要です。
ただし、慢性的な皮膚疾患や、診断が難しい皮膚症状については皮膚科が専門となります。
不安を感じたらまずはかかりつけの内科医に相談し、必要であれば皮膚科を紹介してもらうのも一案です。
- 内科で心の不調も相談できますか?
-
不眠症、頭痛、食欲不振、動悸といった、ストレスが原因で起こる身体的な症状については、内科で相談することが可能です。
内科医は、それらの症状が他の身体的な病気から来ていないかを確認した上で、適切なアドバイスや薬の処方を行います。
内科には「心療内科」という専門分野があるので、もし不調がストレスと関係していると感じる場合は、心療内科の受診も考慮してください。
まとめ・羽曳野市近くで何科に行けば良いか迷ったら内科に相談を
診療科に迷った場合について説明してきました。
成人はまずは内科を受診してください(お子さんの場合は小児科)。
内科医は優れた診断能力を持つ専門家であり、日常的な病気のほとんどに対応できます。
より専門的な知識を必要とする場合は、最適な専門科を紹介してもらえます。
また、かかりつけ医を持つことで、迷った時に気軽に相談できるメリットがあります。
お気軽にお問い合せ下さい
TEL.072-950-0155
受付時間 9:00~17:30
※水曜日、日曜日、祝日、土曜日(午後)は除く
もしくは下記フォームよりお問い合わせください。
問い合わせフォーム