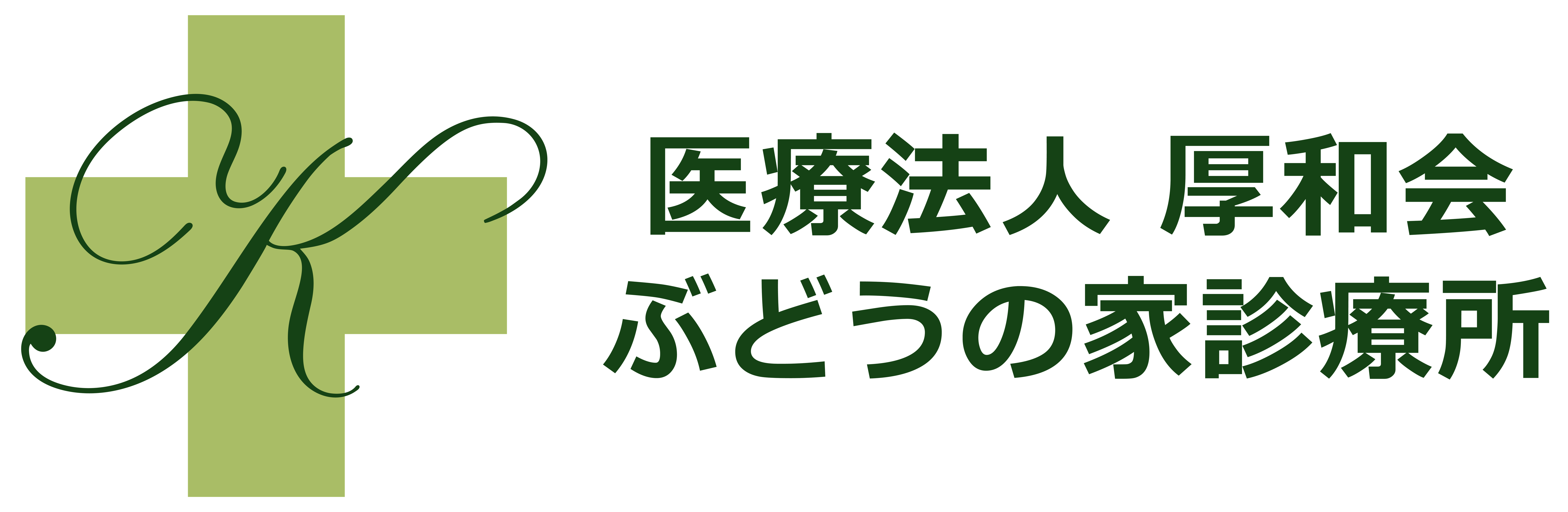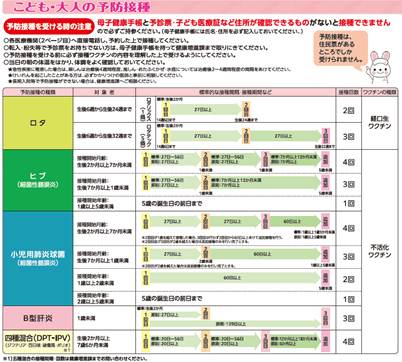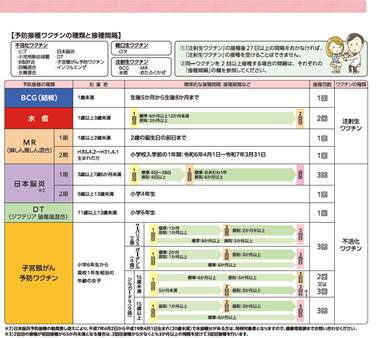予防接種は、感染症の予防や重症化を防ぐために非常に重要です。
羽曳野市では、子どもから高齢者まで幅広い世代を対象に、予防接種の助成制度が整っています。
しかし、「どのワクチンが対象?」「自己負担はいくら?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
この記事では、「定期接種」と「任意接種」の基本的な違いから、インフルエンザ、帯状疱疹 、子宮頸がんワクチンといった主要な予防接種の特徴を詳しく解説します。
さらに、羽曳野市にお住まいの皆様が利用できる公費助成の仕組みや、お子様の複雑な接種スケジュール についても網羅しました。
厚和会では予防接種を行っております。
厚和会で取り扱っている予防接種は下記になります。
●インフルエンザ予防接種
●成人用肺炎球菌ワクチン
●子宮頚がんワクチン9価
●子宮頚がんワクチン4価
●帯状疱疹ワクチン
まずはお気軽にお問い合わせください。
TEL.072-950-0155
受付時間 9:00~17:30
※水曜日、日曜日、祝日、土曜日(午後)は除く
もしくは下記フォームよりお問い合わせください。
問い合わせフォーム
予防接種とは
予防接種とは、感染症を未然に防ぐためにワクチンを体内に入れ、病気への抵抗力(免疫)をつける方法です。
厚生労働省では、次のように説明されています。
『予防接種とは、病気に対する免疫をつけたり、免疫を強くするために、ワクチンを接種することをいいます。ワクチンを接種した方が病気にかかることを予防したり、人に感染させてしまうことで社会に病気がまん延してしまうのを防ぐことを主な目的としています。また、病気にかかったとしても、ワクチンを接種していた方は重い症状になることを防げる場合があります。』
(引用:厚生労働省 予防接種ってなに?)
単に「病気の予防」だけでなく、「かかった場合でも重症化を防ぐ」ことが大きな目的です。また、個人の健康を守ると同時に、地域全体の感染拡大を防ぐため、ひとりひとりが病気への免疫を獲得することが大切です。
なお、予防接種には、定期接種と任意接種があります。詳しく説明します。
予防接種の定期接種と任意接種の違い
予防接種には「定期接種」と「任意接種」の2種類があります。
定期接種とは、予防接種法に基づき接種が勧められているワクチンです。対象年齢内であれば、無料または一部自己負担額を支払うことで受けられます。
一方の任意接種は、法的な義務や助成制度がなく、希望者が自己負担で受けるものです。接種費用は医療機関によって異なります。染症の重症化を防ぐうえで重要な役割を果たします。
定期接種
定期接種は目的に応じて「A類疾病」と「B類疾病」に分類されています。
これは、平成25年の法改正によって、これまでの「一類疾病」「二類疾病」という分類から「A類疾病」「B類疾病」に変更となりました。
A類疾病
A類疾病とは、「人から人にうつる感染症の発生やまん延を防ぐこと、または重症化を防ぐこと」を目的とした予防接種です。
社会全体での感染拡大を防ぐ目的から、集団予防を重点に、接種の努力義務(接種を受けるよう努めなければならないこと)とされています。
対象となる主なワクチン
(参考:厚生労働省予防接種・ワクチン情報)
B類疾病
B類疾病は、「個人の発病や重症化を防ぐこと」を主な目的とする予防接種で、主に高齢者が対象です。
感染症そのもののまん延を止めるというより、重症化防止の観点から推奨される接種で、努力義務はありません。
対象となる主なワクチン
いずれも自治体ごとに助成内容や自己負担額が異なります。
羽曳野市では、原則として65歳以上の高齢者に対して、接種費用の一部を助成しています。
任意接種
予防接種法に基づかない「希望による接種」で、定期接種の対象外となるワクチンを指します。
主に国内での感染予防や重症化予防を図るためのワクチンです。費用は基本的に、全額自己負担となります。
主な対象ワクチン
なお、定期接種の対象年齢を過ぎた方が接種する場合も、任意接種の扱いとなります。
海外渡航者や基礎疾患のある方は、医師に相談しながら任意接種を受けることで、感染症リスクを大幅に減らすことが可能です。
(引用:第34回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料|厚生労働省)
予防接種の種類と特徴
日本では、年齢や健康状態に応じて推奨されるさまざまなワクチンがあります。
ここでは主な予防接種について、特徴や効果、副反応などを紹介します。
インフルエンザ予防接種
インフルエンザは例年冬に流行するウイルス感染症で、発熱や倦怠感、筋肉痛などの症状を引き起こします。特に高齢者や基礎疾患のある人では、肺炎や脳症などの重い合併症を起こすこともあります。
【特徴】
インフルエンザワクチンは、毎年流行が予測されるウイルス株をもとに作られ、感染や重症化を防ぐ効果があります。2025年度は3価ワクチンが導入されており、すでに接種が進んでいる状況です。接種しても感染することがありますが、発症しても症状を軽くする効果が期待できます。
【接種回数】
- 生後6ヵ月以上13歳未満:2回
- 13歳以上:通常1回(2回接種も可能)
なお、2歳以上~19歳未満には、鼻に噴霧するワクチンもあります。こちらはシーズンごとに1回です。
【副反応】
注射部位の赤みや腫れ、発熱などが一時的に見られることがあります。
(参考:季節性インフルエンザ|厚生労働省)
新型コロナワクチン予防接種
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、主に発熱や喉の痛み、呼吸器症状などを引き起こす感染症です。重症化すると肺炎や呼吸不全を生じることがあり、特に高齢者や基礎疾患を持つ方では注意が必要です。
令和6年度以降は、定期接種(B類)として実施されます。
【特徴】
その時期に流行しているウイルスの型に合わせて作られたワクチンを使うことで、よりよく効くことが分かっているため、新型コロナワクチンの種類は、毎年変わります。
【接種回数】
新型コロナワクチンの接種回数は、年齢や体の状態によって異なります。
毎年使われるワクチンが変わるため、その年に必要な回数は自治体の案内等をご確認ください。
【副反応】
注射部位や筋肉、関節の痛み、疲労、頭痛が現れることがあります。また、まれにアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)が起こります。
(参考:新型コロナワクチンについて|厚生労働省)
成人用肺炎球菌ワクチン
肺炎球菌は、肺炎や髄膜炎、敗血症などの原因となる細菌です。
肺炎球菌ワクチンには、23価肺炎球菌莢膜多糖体ワクチン(PPSV23)と13価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV13)、15価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV15)、20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)、21価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV21)の5種類があります。
なお、任意接種で用いられてきたPCV13は、より多くの型をカバーするPCV20(プレベナー20®)に実質的に置き換わっています。
23価肺炎球菌莢膜多糖体ワクチン(PPSV23)は、定期接種対象疾患(B類疾患)として、対象者には公費助成があります。
接種対象者や年齢により接種方法や回数が異なります。
(参考:予防接種に関するQ&A集2024 肺炎球菌感染症|日本ワクチン産業協会)
子宮頚がんワクチン
子宮頚がんの原因の多くは、ヒトパピローマウイルス(HPV)感染です。HPVは性的接触を通じて感染しますが、ワクチン接種により予防できます。
なお、接種を逃した平成9~20年度生まれ(誕生日が1997年4月2日~2009年4月1日)の女性は、キャッチアップ接種が無料です。
※令和7年3月31日までに1回目を接種すれば、令和8年3月31日までの間、残りの接種を公費(無料)で受けられます。
【特徴】
公費接種では2価・4価・9価の3種類のワクチンが使用可能です。
9価(シルガード9®)は4価(ガーダシル®)より予防できるHPVの種類(型)が多く、子宮頸がんの原因の80~90%をカバーします。
【接種回数】
ワクチンの種類や年齢によって2~3回です。
【副反応】
主な副反応として注射部位の痛み、腫れに、注射の痛みや不安・興奮などによる失神が報告されています。また、まれにみられる副反応としてアナフィラキシーやギラン・バレー症候群などがあります。
(参考:子宮頸がんの予防に有効なHPVワクチンとは?|政府広報オンライン、ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~|厚生労働省)
帯状疱疹ワクチン
帯状疱疹は、水ぼうそうの原因ウイルス(VZV)が、体内で再活性化して発症する病気です。強い痛みや神経障害を残すことがあり、50歳以上の方で発症が増えます。
帯状疱疹の予防ワクチンは生ワクチンと不活化ワクチンの2種類あります。
【特徴】
帯状疱疹やその合併症に対する予防効果は以下の通りです。
帯状疱疹に対する効果 生ワクチン 不活化ワクチン 接種後1年時点 6割程度の予防効果 9割以上の予防効果 接種後5年時点 4割程度の予防効果 9割程度の予防効果 接種後10年時点 ― 7割程度の予防効果 (引用:帯状疱疹ワクチン|厚生労働省)
【接種回数】
生ワクチンは皮下に1回、不活化ワクチンは筋肉内に2回接種します。
【接種制度】
2025年度から2029年度までの5年間は経過措置として65歳、70歳など特定の年齢は「定期接種」(公費助成あり)となりました。それ以外の50歳以上は「任意接種」です。
【副反応】
どちらも注射部位の痛みや腫れがありますが、不活化は筋肉痛や疲労が比較的強く出ることがあります。
(参考:帯状疱疹ワクチン|厚生労働省)
予防接種にあたっての注意点
予防接種を安全に受けるためには、いくつか知っておきたいポイントがあります。
定期接種や任意接種の費用助成は、お住まいの自治体(市区町村)によって対象者や助成額が異なります。
ワクチン接種後は、免疫がつく過程で発熱や接種部位の腫れなどの副反応があらわれることがあります。
予防接種の資格
定期接種の場合、対象年齢や居住地、基礎疾患の有無によって公費助成の対象かが決まります。
例えば、高齢者のインフルエンザワクチンは定期接種(B類)です。65歳以上の方や、60歳以上65歳未満で心臓や腎臓などに重い障害がある方が対象で、自治体の補助があります。
それ以外の一般の方が接種する場合は任意接種となり、原則全額自己負担です。
予防接種の対象
日本の予防接種は、主に厚生労働省が推奨する標準的な接種年齢に基づきスケジュールが組まれています。特に赤ちゃんや子どもは感染症にかかると重症化しやすいため、多くのワクチンが生後2か月から開始されます。
接種開始年齢別ワクチンは次の通りです。
なお、対象年齢を外れた場合でも、任意接種として自費で接種できるワクチンもあります。
生後2か月から
赤ちゃんの予防接種は、免疫が低下する生後2か月から始まります。
この時期に接種が推奨されるのは、B型肝炎ワクチン、ロタウイルスワクチン(1価または5価)、そして子どもの肺炎球菌ワクチンです。
また、2024年4月からは、これまでの4種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ)にヒブ(Hib)ワクチンを加えた「5種混合ワクチン」が定期接種として導入されています。
生後5か月から
結核による重篤な感染症を予防するためのBCGワクチンの接種が推奨されます。
1歳頃から
MR(麻しん・風しん混合)ワクチン、水痘(みずぼうそう)ワクチンです。また、子どもの肺炎球菌ワクチンや5種混合ワクチンの追加接種もこの時期に行われます。
(参考:1歳頃から推奨される予防接種|厚生労働省)
3歳から
日本脳炎ワクチンの1期接種を行います。
日本脳炎はウイルスを持つ蚊によって媒介される感染症です。
第1期では、6日から28日までの間隔をおいて2回接種し、そのおおむね1年後に3回目の追加接種を行います。
(参考:3歳から推奨される予防接種|厚生労働省)
5歳から
MR(麻しん・風しん混合)ワクチンの2期目接種が始まります。
1歳で接種した免疫をさらに強化し、集団生活での流行を防ぐための重要な追加接種です。小学校入学前の1年間(年長の年度)が対象期間です。
(参考:5歳から推奨される予防接種|厚生労働省)
9歳から
日本脳炎ワクチンの2期の接種が始まります。
これは3歳代で開始した1期(計3回)の追加接種にあたります。9歳~10歳までの間に1回接種します。
(参考:9歳から推奨される予防接種|厚生労働省)
11歳から
DT(ジフテリアと破傷風の混合)ワクチンを摂取します。
乳幼児期に接種した4種混合や5種混合ワクチンの追加接種にあたり、基礎免疫をつけた後の免疫をさらに強固にするために行われます。標準的には11歳の1年間に1回接種します。
(参考:11歳から推奨される予防接種|厚生労働省)
12歳頃から
小学6年から高校1年相当の女子を対象に、子宮頸がんの原因となるHPV(ヒトパピローマウイルス)の感染を防ぐHPVワクチンの定期接種が行われます。
また、接種機会を逃した方(平成9~20年度生まれ)のキャッチアップ接種も実施中です。
65歳から
65歳からは、重症化予防を目的としたB類疾病の定期接種が中心となります。
対象は、季節性インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、そして高齢者の肺炎球菌ワクチンです。また、2025年度からは帯状疱疹ワクチンも特定の年齢(65歳、70歳など)を対象に定期接種に加わりました
予防接種の副反応
ワクチン接種後は、免疫獲得の過程で副反応が起こることがあります。
一般的な反応は発熱、倦怠感、接種部位の痛みや腫れです。
まれに、ワクチンごとの特徴的な反応も報告されています。
- BCG:接種後、腋窩(わきの下)のリンパ節が腫れることがあります。
- ロタウイルスワクチン:腸重積症(腸の一部がほかの部分に入り込んで、腹痛などを起こす病気)のリスクが高まることが知られています。
- 風しんワクチン:ごくまれに血小板減少性紫斑病。
- おたふくかぜワクチン:まれにウイルス性髄膜炎を発症することがあります。
(参考:予防接種とは?|東京都医師会)
予防接種の時期とスケジュール管理のポイント
感染症から身を守るために、予防接種は最適な時期に受けることが大切です。
特に乳幼児期は多くのワクチンが推奨されていますし、季節性ワクチンや特定の年齢で推奨されるものもあります。複雑な日程を管理し、接種漏れを防ぐためのポイントを解説します。
予防接種の時期
赤ちゃんの予防接種は、免疫が低下する生後2か月から始まり、多くのワクチンが1歳までに集中します。季節性インフルエンザは通常、流行前の10~11月頃、帯状疱疹は50歳以上が対象です 。
接種漏れを防ぐために、母子健康手帳やお薬手帳への記録、予防接種スケジュール管理アプリの活用などが考えられます。管理しやすい方法を見つけると良いでしょう。
予防接種のスケジュール
最新の予防接種スケジュールは、国立感染症研究所のホームページで確認できます。
なお、乳幼児期は接種回数が多いため、日本小児科学会は同時接種を推奨しています。
医師が特に必要と認めた場合、複数のワクチンを同じ日に受けることが可能です 。
(参考:日本小児科学会の予防接種の同時接種に対する考え方|日本小児科学会)
なお、羽曳野市でも予防接種のスケジュールを公開しています。
(引用:子どもの定期予防接種|羽曳野市)
詳細は、羽曳野市の予防接種に関するホームページをご確認ください。
予防接種の注意点
接種当日は、母子健康手帳、記入済みの予診票、健康保険証、子ども医療証などを忘れずに持参しましょう。
熱があるなど体調が悪い場合は、医師と相談しながら接種の延期も考慮します。
接種後は、アレルギー反応(アナフィラキシー)などに備え、医療機関で15分~30分程度は安静にし、体調の変化を観察することが重要です。
羽曳野市の予防接種について
羽曳野市での予防接種は、市に住民票がある方が対象です。
接種には市の予診票が必要で、出生月の翌月末ごろに冊子で送付されます。
また、それ以降は対象年齢になると住民票の住所に予診票が送られてきます。
羽曳野市での助成対象の予防接種は、主に次の通りです。
このように市が助成する接種もありますが、任意接種は原則として全額自己負担です。
小児の定期接種も対象年齢を過ぎると自己負担となるため注意が必要です。
(参考:羽曳野市予防接種ホームページ)
羽曳野市でのインフルエンザ予防接種事業
羽曳野市では、高齢者の重症化予防を目的としたインフルエンザ予防接種事業(定期接種)を実施しています。この事業は、対象となる市民の接種費用を一部助成するものです。
ここでは、令和7年度の具体的な助成対象者や接種料金について解説します。
羽曳野市のインフルエンザ予防接種助成を受けられる人・実施期間
【対象者】
令和7年度の高齢者インフルエンザ予防接種の助成対象者は次の通りです。
- 接種時に65歳以上の羽曳野市民
- 60歳から65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能やHIVによる免疫機能に重い障害を有する羽曳野市民
【実施期間】
令和7年10月1日から令和8年1月31日までです。
詳細は羽曳野市のホームページで確認してください。
(参考:令和7年度高齢者インフルエンザ及び新型コロナ予防接種について|羽曳野市)
羽曳野市のインフルエンザ予防接種の料金
高齢者インフルエンザ予防接種の助成対象者は、自己負担金1,000円で接種可能です。
助成対象者以外の方が接種する場合は任意接種となり、費用は全額自己負担となります。
料金は医療機関により異なるため、直接お問い合わせください。
なお、当ぶどうの家診療所にてインフルエンザワクチンの接種をご希望の場合は、3,900円で接種いただけます。
感染症の予防や重症化を防ぐために予防接種をご検討ください
予防接種は、ご自身だけでなく、ご家族や地域社会を感染症から守る最も有効な手段の一つです。
この記事では、複雑な予防接種の種類(定期接種・任意接種)、子どもの接種スケジュール、そして羽曳野市が提供する公費助成制度について解説しました。
特にHPVワクチンのキャッチアップ接種や帯状疱疹ワクチンの定期接種化など、最新の情報も重要です。
「どのワクチンをいつ受けるべきか」迷った際は、ぜひ『ぶどうの家診療所』へお気軽にご相談ください。
厚和会では予防接種を行っております。
厚和会で取り扱っている予防接種は下記になります。
●インフルエンザ予防接種
●成人用肺炎球菌ワクチン
●子宮頚がんワクチン9価
●子宮頚がんワクチン4価
●帯状疱疹ワクチン
まずはお気軽にお問い合わせください。
TEL.072-950-0155
受付時間 9:00~17:30
※水曜日、日曜日、祝日、土曜日(午後)は除く
もしくは下記フォームよりお問い合わせください。
問い合わせフォーム